活動報告
ACTIVITY
都議会報告
平成25年2月28日 定例会 一般質問
1.教育施策について
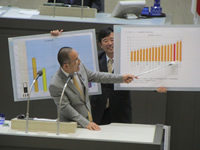 最初に、都立中学及び中等教育学校前期課程における給食時間の違いの実情と食育について伺います。
最初に、都立中学及び中等教育学校前期課程における給食時間の違いの実情と食育について伺います。
これは、一日の三食合計の平均時間を示したグラフです。
一位は勿論、美食のフランス・・・・
諸外国の学校給食の在り方については様々です、例えて言いますと・・・・
米国 12:25~13:05 40分間
英国 12:15~13:30 1時間15分間
オーストラリア 12:30~1:30 1時間
フィンランド 11:30~12:15 45分間
韓国 12:10~13:00 50分間
ケニア 12:40~14:00 1時間20分
給食の内容は、いつも同じギゼリ(トウモロコシと豆を煮たもの)だけである。
フランス 11:30~13:30 2時間
給食が長い分、後におされるのでしょうか。(エコール・グループ・サン・トーマス)これは現地時間で夜の6時お母さんが、子供を迎えに来ていました。日本でも同じ様にゆっくり給食に時間をかける学校があります。福岡市南当仁小学校です、ここは給食に50分間、それとは別に昼休みを45分間取っています。登下校の時間を決められていて、その中で給食時間が決まるというものでなく、どちらもしっかりと給食時間を取っています
私は給食をゆっくり取ることが心と体を養う「食」につながると考えます。
良く咀嚼することは胃の負担を軽減し、脳に刺激を与え健康に寄与します、そして何より友情を育む子供たちとのコミュニケーションの時間が増えるということです。
そこで、都立中学及び中等教育学校前期課程、全10校における平成23年度の給食時間の実態は、区市町村の小・中学校についても同じ傾向が見られますが、配膳をして、食事して、かたずけて、となると実質食事に20分ぐらいが多いのでしょうか? 20分から40分までとバラつきがあると伺っております、さて本日は都立中高一貫教育校の、給食時間の違いの実情と食育における給食の役割について伺います。
次に、都立高校改革推進計画について伺います。
猪瀬知事の「言葉の力」の著書には、日本人の「言語技術」に対する危機感や言語力を重視した人材発掘・人材育成についてふれられています。
東京都が目指す「都立高校改革推進計画」の中には、世界で活躍できる人材育成を目指す国際バカロレア認定の取得があります。
 さて、私は2月9日から15日までフランスとドイツに行き、国際バカロレアの認定を受けた高校を訪問しました。
さて、私は2月9日から15日までフランスとドイツに行き、国際バカロレアの認定を受けた高校を訪問しました。
国際バカロレアは世界各国のインターナショナルスクールや現地国の卒業生に国際的に通用する大学進学資格を付与する仕組みです。
国際バカロレア認定校となる為には、ジュネーブに本部を置く、国際バカロレア機構から認定を受ける必要があります。国際バカロレアは、「異なる文化を理解し世界の平和に貢献する等」を教育理念としており、その教育プログラムは世界的に高い評価を得ています。
都立高校でも将来的に国際バカロレアの認定を目指すとのことですが、まず、都立高校において国際バカロレアの認定の取得を目指す目的について伺います。
 また、パリにある国際バカロレア認定校では、教員の方からお話を伺いました。「認定を取得することもまた、認定受けてからの維持も大変である。」とのことでした。認定校では数学や歴史などの科目について、英語・フランス語・スペイン語のいずれかの言語で授業をすることが義務付けられています。認定の取得に向けては、多くの課題があると思います。どのような課題があり、その解決に向けどのような取り組みを進めていくのか、伺います。
また、パリにある国際バカロレア認定校では、教員の方からお話を伺いました。「認定を取得することもまた、認定受けてからの維持も大変である。」とのことでした。認定校では数学や歴史などの科目について、英語・フランス語・スペイン語のいずれかの言語で授業をすることが義務付けられています。認定の取得に向けては、多くの課題があると思います。どのような課題があり、その解決に向けどのような取り組みを進めていくのか、伺います。
次に、小学校における動物飼育について伺います。
昨今、子供の いじめや自殺が大きな問題となっております。大津市の男子生徒自殺問題や、昨年12月8日にいじめにより自殺した、世田谷の女子中学生徒事件は記憶に新しいところです。後者はスカートをめくられ追いかけられたり、20分の給食中ずっと「きもい」「うざい」と暴言をあびせられ続け、失意のうちに特急電車に飛び込み自殺をしました。止まらない自殺に深い悲しみを覚えます。
さて、私は小学校における動物飼育を学ぶことが、いじめ・自殺対策の特効薬と考えます。
知事の家にも愛犬がいると聞いています。私の家にも16年いた愛犬ラッキーが昨年の暮れに亡くなり、家族はもとより近所の犬仲間もとても悲しみました。
同じように、終末看護をした動物に立ち会った子供たちは、「あれが悪くて死んだか?」「これが悪かったか?」と自分たちの行った看護について嘆きます。
ある動物の死を体験した子は、「今まで簡単に『死ね!』と言っていたけど、こんなに悲しいとわかって、もう言えない。」と作文に書いています。
世話をする動物の死に出会うこともまた、命の大切さに気付かせる大事な機会と考えます。子どもたちは動物に愛情をいだき、いやされ、世話の楽しさを知り、責任もち、笑い、涙します。子供たちが動物と直接触れ合う事はどんな高い教材よりも、心と命を学ぶことができるでしょう。
大阪府寝屋川市では市内12中学の生徒役員が集まって、いじめの実態を調査、それを参考にストーリーをつくり、生徒が出演して「いじめ撲滅劇」を2008年夏から上演しています。以後、いろいろないじめを、いじめる側、いじめられる側を演じ、毎年、新しい劇が生まれ,後輩たちに受け継がれています。また、劇はDVDにして市内の全小・中学校に配布されています。まだ頭の柔らかい10代のうちにいじめや自殺問題に関心を持つことは重要と考えます。
東京都内の小・中学校では毎年数人の児童や生徒が自殺しています。動物のふれあいやDVDなどを活かし「東京都の小・中学生の自殺者0の目標」をかかげてはいかがでしょうか。
東京都の中長期的において自殺者をなくしていく道筋になると確信します。
そこで、都教育委員会は、平成23年度から、獣医師会の協力を得て「動物ふれあい教室」を実施しておりますが、これは、子供たちが動物と直接触れ合う機会として、大変よい取り組みだと思います。
しかし、「動物ふれあい教室」は、一校につき年に一回、20校での実施です。この取組に加えて、各学校が家庭や地域の力を借りて、子供たちに動物と触れ合える機会をたくさんつくることも重要ではないでしょうか。
そこで、小学校における動物飼育活動を、教職員の共通理解や協力はもとより、家庭や地域と連携した取組を進めることが大切だと考えますが、教育長の見解を伺います。
また、私はこれまでも、小動物の飼育を通して、子供たちが命の大切さを学ぶ教育が重要と述べてきました。
この素晴らしい教育活動を充実させるべきと考えます。教育長の見解を伺います。
2.首都大学東京の国際化について
首都大学東京はイギリスのタイムズ社が発表している国際的な大学ランキングでは、世界に1万を超える大学があるといわれている中、世界で266位、国内で7位と国際的にも高い評価を得ています。
しかし、その一方で、国際化の指標の一つである留学生の受入数、海外への派遣数については、首都大学は増加傾向にあるものの、昨年の受け入れは355人、派遣数に至っては、一昨年で44人であります。交換留学協定締結校においても世界には200ヶ国ある中で8ケ国・地域11大学にとどまてっています。
首都大学東京を一層発展させていくためにも、国際化の推進が不可欠ですご所見を伺います。ご静聴有難うございました。
